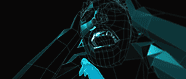端的にいうなら作中の「ロビン西のアザー・ワールド」こそ万博的多幸感に満ちている。しかし僕個人がいちばん万博的だな、と感じるのは鯨到来の大津波だったりするんだけどね。三菱未来館なるパヴィリオンで体験した展示……というかアトラクションは、世界の終末を思わせる火山の噴火や大嵐などの実写映像を「動く歩道」の両壁面に映しだし、観客にカタストロフを体感させるというものだったが、その中に大津波もあって、当時小学1
年の僕はたいそう恐ろしかった記憶がある。まさに人類終末の様相だが、この恐怖の回廊を過ぎればバラのような未来像が待っているのだ。このシナリオは当時の大人にすれば「破壊による解放、そして再生への希望」といったところなのだろうが、それは幼な心にもなんとなく理解できるものではあった。そんな想い出に耽っているところで西クンのあの言葉が聞こえてきはしないか。……「恐怖は自分の中にある。自分のマインド次第でいくらでも変化する。心の中に灯りをともして、その光をデカくして、楽しいと思ってみて。嘘でも心の中で楽しいって感じてみて。それだけで今までと急に違ったモンが見えるやろ」
他にも60 年代的テーゼを本作の中に認めるのは容易だ。性的束縛からの解放、ジェンダーの混淆、宇宙意識との一体化。もちろんヤンちゃんのモダン・アートもそうだ(ついでにジイさんのエロオブジェも)。そもそも“ミョンちゃんへの愛”を手段とし、インナーワールドを突き詰めることで宇宙とリンクするという西クンのエクソダスは、ミクロとマクロの、アートマンとブラフマンの一元性を求める東洋的解脱法に通ずる。「神さま」がクラフトワーク的テイストのCG
で西クンにイヤガラセするシーンなども、フィリップ・K ・ディック(彼も60 年代の落とし子であった)が『ヴァリス』で用いた「巨大にして能動的な生ける情報システム」などという言葉をつい思い浮かべてしまうのだが。 |
 |
しかもこの「神さま」、さまざまな形態にめくるめくメタモルフォーズしていく。それは今までの漫画史をすべてブチこんだようなナンセンスでアホらしいものだが、どこかしら『ビートルズ
イエローサブマリン』('68 )に登場する“Ph.D ”=“Nowhere Man ”を想起させはしないか。
そうなのだ。本作そのものが、この60 年代に出現したアニメーション映画の金字塔を彷彿とさせるのである。勇猛果敢な実験性、制作時の動画テクニックを総動員したヴァラエティ、斬新だが確固とした美意識の存在。
コンピュータの導入があたりまえになった現代のアニメーションから、急速に欠けつつあるのは「美意識」である。確かにさまざまなマテリアルの使用が自在にはなった。だが、それらを混在させたときの質感の違いに、あまりに無頓着なアニメ(あるいは実写をアニメ的に加工した映画)が多すぎる。そうした現状の中で、本作が達成したコンクレートは相当繊細なものといえるだろう。
それでいて、中盤挟まれるシネ・バレエにきっと古くからのアニメーション・ファンは狂喜するに違いない。なんせ、ここで使われる音楽はリストの「ハンガリー狂詩曲第2
番」なのだ! これをネタにして、ライヴァル的関係にある二大キャラが同年に二本の短編を作り上げているのはカートゥーン史上有名な事件。一本はワーナー・ブラザーズのバッグス・バニーもの『Rhapsody
Rabbit 』('46 、フリッツ・フリーレング監督、邦題『バニーのピアノリサイタル』etc.)、もう一本はMGM のトムとジェリーもの『TheCat
Concerto 』('46 、ハンナ&バーベラ監督、邦題『猫の演奏会』or 『ピアノ・コンサート』)。すぐれて音楽的な、いずれ劣らぬ傑作であるから、これは『クレしん』シリーズ恒例のミュージカル・シーンで卓抜した手腕を示してみせた湯浅によるオマージュであると捉えていいだろう。 |